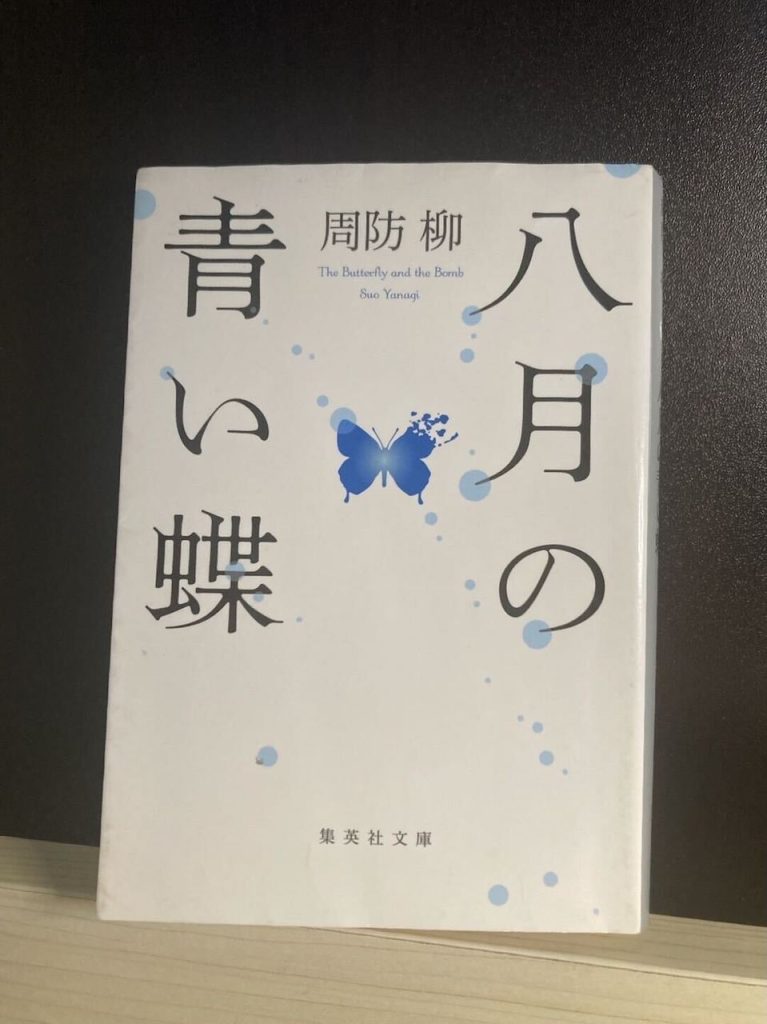著者:周防柳 出版社:集英社 出版年:2016年(単行本:2014年)
太平洋戦争末期の1945年8月6日は広島にアメリカからの原子爆弾が落とされた日だ。本書は当時の広島を舞台に少年亮輔の少年期の記憶を基盤とした小説作品である。東京で働くきみ子は父・亮輔の末期白血病をきっかけに実家の広島に帰郷する。最期を自宅で過ごすための準備を母としていたところ、実家の仏壇から翅が少し焼けた青い蝶の標本を見つける。その標本は亮輔の少年の頃の忘れられない日々を象徴するものだった。ここで物語は亮輔の少年時代へと戻る。軍人である亮輔の父の愛人・希恵が亮輔の家に移り住み、2人は息子と愛人という立場を超えて親しくなる。昆虫学者の娘であり、自身も昆虫採集を愛好していた希恵は亮輔と日々昆虫採集や標本作りを繰り返して仲を深める。8月6日の朝、希恵と蝶の羽化を見にいく約束をしていた亮輔だったが、2人の関係をよく思わない亮輔の母の目論見で街の作業に動員されてしまう。亮輔が約束を心配する中、8時15分に広島に原爆が投下される。
戦争を題材に据えた作品の多くで描かれるのは「喪失」だろう。自身よりも肉親や兄弟、友人、恋人等の親しい人々、財産や時間を奪われ、失う。戦禍の悲しみを最もよく表し、それゆえに戦争へ反対する意思はより一層強いものになる。本書もまた、戦争による喪失が物語の根幹を成す。亮輔は初恋の女性を原爆によって喪ってしまう。ただ、この作品がそれだけで終わらないのは人物たちの重厚な個人史を挿入することによって表される欲望や葛藤である。主人公の亮輔だけではなく、亮輔の両親、希恵、亮輔の妻と娘といった登場人物一人ひとりの生い立ちと心情に対し、手抜かりなく焦点が当てられる。人物たちの生涯を追いかけていると20世紀初頭、戦時中の日本に暮らした彼らの実に多面的な姿―時にはその矛盾した心や秘めた個の欲望までもが示される。彼らの生きるための思想の根幹、時に心の奥底に秘めたり、彼らの見ないふりをしていた気持ちが小説ゆえに鮮明に描かれる。それらの記述は悲惨さだけが記憶しがちな読者の表層的な戦争への理解をより深い部分へと誘い人間の歴史に対峙させる。戦争中の空気だからこそ亮輔の母が確立したアイデンティティ、希恵と亮輔、そして亮輔が誰にも明かさず隠した胸のうちに秘めた歴史は、大衆に共有された戦争の記憶、被害地域の人々の保持する個々の物語、それらとは完全に自由な状態で亮輔の意思として物語の中だけに存在する。戦争の記憶という公共化され歴史化されがちな物語から一度離れ、個人史という観点から戦争という事象を見つめ直す作品と言えるだろう。
また、しばしばそうして戦禍を這い上がった亮輔たちの心情描写の中には葛藤や後年の自身の経験からくる傷との向き合い方に煩悶する場面も描かれる。生き抜いた人間が「生き残ってしまった」という自責や誰かの生命維持のためのきっかけを押し除けて生き延びた可能性があることの安堵と呵責を自分の中で葛藤し、時にはなんとか押し除けて生きていくしかないことの後ろめたさを伴う苦痛がありありと浮かび上がってくる。大きなものに翻弄され、自分の大切なものの正当性を守る、あるいは自分自身の人生における過失の部分を覆い隠して自分自身を守ろうとするために。そうしなければ生きていく望みすらも失われてしまうからだ。
そうして考えてみると、戦争の罪とは、この袋小路の状態を人に強いることとも言えるのかもしれない。戦争によって直接的にしろ間接的にしろ、人は身体的に大きなダメージや苦しみを受ける。経済的な意味での立ち直りがあったとしても、背負わされてしまった戦争による歪みやその葛藤は消えはせず、容易に共有したり言語として言い表すことのできるものではない。傷をおった人々は互いの傷に触れぬように口をつぐむことは決して珍しいことではなかった。亮輔の父は軍人であり戦後、戦中下の加害を糾弾される立場に転じてしまう。しかしその父もまた戦地で恐怖を味わい、何よりも自身の今までの行動を全て否定され、置き去りのような状態になってしまう。加害者として見なされがちな軍人が憔悴した被害者としても描かれているのだ。対して、亮輔は軍人の子であるが、原爆投下の際爆心地の1.8kmで被爆して生き残った少年として描かれている。「加害者」の家族、そして間近で原爆の被害を受けた「被害者」としての一見正反対のようにも見えるパーソナリティが亮輔の中では共有されている。本作の主人公・亮輔のモデルは、作者である周防の父である。生前被爆した経験を積極的に語ることはなく、また家族も父からそうした記憶を聞き出すことに躊躇してしまったという。周防は実父の白血病を契機に「今書かねば」と発起して年月をかけて本作の執筆に取り組んだが、父の口からその記憶を詳細に聞き出すことは叶わなかった。無闇に語ることを避けた父の姿について、集英社の読書雑誌『青春と読書』に掲載された当時のインタビューで同作を選考した小説家の村山由佳にこう語っている(文末註1)。
「
周防:父が何も語らなかったのは、自分の父親が軍人だったからだと思うんです。父親をかばいたい一方で、同級生のほとんどが亡くなっていたのは「お父ちゃんのせいだ」という気持ちがどこかにあった。
村山:周防さんのお父様は、本当に主人公(註:亮輔)のような立場にいらしたのですね。被爆した自分は被害者だけど、心の中には加害者意識があった、という。
周防:自分が責められるのはいやだ、でも仲の良かった同級生は消えてしまっている。だからどうしたらいいかわからない、何も言えない。半分に引き裂かれた状態だったから沈黙したのだろうというのが、考えに考えた上での私の想像です。
村山:贈賞式のスピーチでおっしゃっていた「人は一番大事なことは言わない」という言葉、すごく印象的でした。
周防:口に出せるようなことは大したことじゃないのです。父は偉人などではない平凡な田舎のおじさんでしたが、そういう人にして沈黙するようなことを抱えていた。つまりは、誰にでもそういう抱えているものがあるということなんですね。
」 (「対談 第26回小説すばる新人賞 周防柳『八月の青い蝶』 村山由佳 周防柳 父に聞けなかったこと……」, 『青春と読書 2014年3月号』, 集英社編, 2014年3月, pp.16-17)
戦争文学の持つ機能が「喪う」ことの恐ろしさを喚起するだけのものではないことを本書からも読み取ることができる。個人の家族構成や直面した出来事、その時どこにいたか…戦争は大衆を巻き込む事象であり、それゆえに個人個人にまで焦点を当てればそれだけの背景が存在する。瞬間瞬間を切り取ったパーソナリティや立場が折り重なって、混ざり合ってその生を作り上げている。閃光に焼かれてまもなく命を落とした人もきっとそうだったのだ。簒奪と喪失という戦争の恐怖に加え、個人が後ろめたさや呵責の織り混ざった繊細な苦しみに付き纏われ続けて生きることに対する苦い行き詰まり、そしてその苦しみの中でも残された自分の命や残りの人生を強かに掴み取ろうとする執念は時に反目しながら個人の身体の中で生きているのだと、周防は文学の形でそれを示した。
戦争文学として読み継がれてきた作品は多い。大岡昇平、江戸川乱歩、野坂昭如、坂口安吾といった多くの文筆家が時には自身の記憶を引き出したり投影することによって物語を紡いできた。まさしく人の血や痛みが練り込まれた作品分野であり、本作もまたそれらと同様に人の命でできた文学作品の一つであることは間違いない。その上で、この『八月の青い蝶』において周防は個々の人物の歴史を作中で丹念に集積することによってさらに苦しみと生きることの決意の中で語り継がれることを目的としない歴史を再現している。それは戦争による怪我、死別、困窮をその肌身に感じないまま生きてきた人々が圧倒的に多い現代の日本において、平和教育や反戦運動を表層的に訴えることの愚かしさを指摘して、語られないからこそ存在する痛みの記憶を知覚させる。喪失の恐怖だけでない、個人の生き方に後ろめたさを付随させ、行き詰まらせながら生かす苦しみというものが戦争にはあるのだと訴えているかのようだ。2010年代という戦争記憶風化の危惧と、歴史の所在およびその取り扱いについての一つの可能性を示す作品として本作は21世紀の戦争文学としてこれからも羽ばたいていくだろう。
註1:本作は集英社が毎年開催している「小説すばる新人賞」の第26回(2013年)の受賞作である。タイトルは『翅(はね)と虫(むし)ピン』であり、単行本出版時に『八月の青い蝶』に改題された。村山由佳は本賞の選考委員であり、本作を推挙した1人である。以下の対談は受賞作品である本作の単行本化にあたり収録されたものである。
参照:「対談 第26回小説すばる新人賞 周防柳『八月の青い蝶』 村山由佳 周防柳 父に聞けなかったこと……」, 『青春と読書 2014年3月号』, 集英社編, 2014年3月, pp.13-17
書き手:上村麻里恵