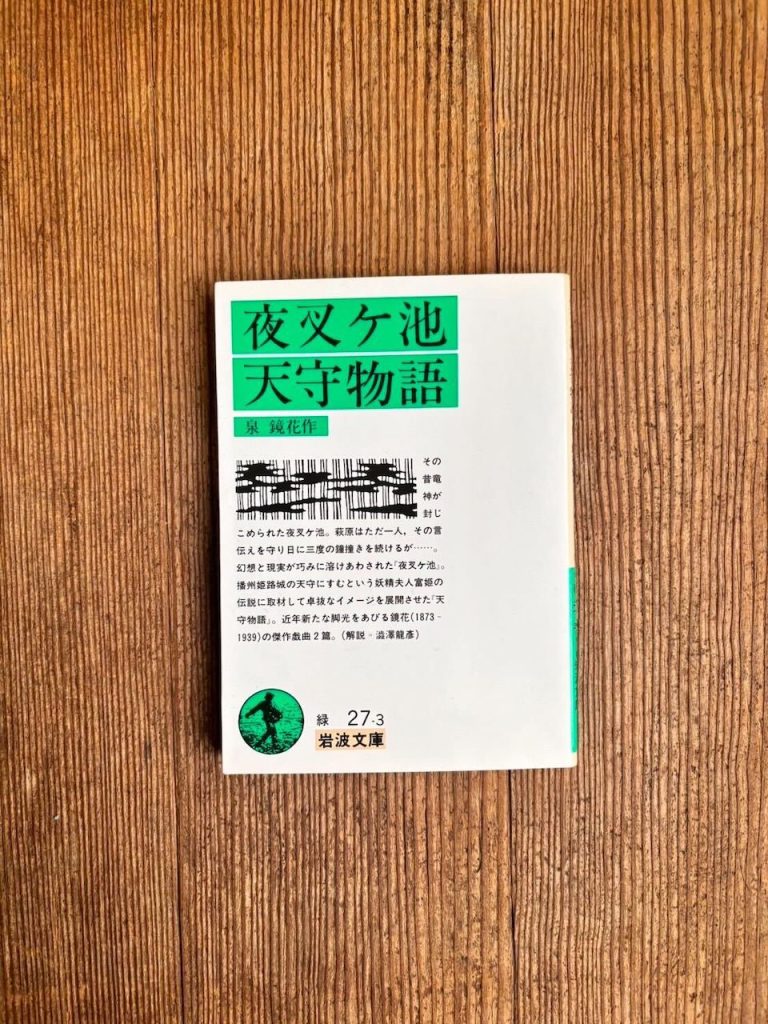作家:泉鏡花 出版社:岩波書店 出版年:2017年(1984年初版)
誰しも、現実とは様相を異にする世界への思慕を抱いているだろう。フィクション作品に触れるとき、私たちは物語のあちら側と自分たちのいるこちら側という境界を強く意識する。登場人物や物語の背景への共感、理解あるいは拒絶という反応を通してその境界を越境することが、文学の楽しみ方の一つではないだろうか。とりわけ幻想文学というジャンルは、妖怪や妖精といった不可思議な存在や現象によって、あちら側とこちら側の分断を明白にしている。
日本の幻想文学においては、泉鏡花なくしてその真髄を語ることはできない。幻想小説の代表作『高野聖』のほか、『婦系図』や『外科室』などロマン主義的な悲恋をモチーフとした小説も著名である。今回紹介する『夜叉ケ池・天守物語』は二作とも小説ではなく戯曲の形式で、幻想性とロマン性という泉作品のエッセンスが存分に詰まった作品だ。
主人公の荻原晃は竜神が棲むと言われる「夜叉ケ池」の近くで、言い伝え通り毎日鐘をつきながら百合という女と暮らしている。そこにかつての親友・山沢学円が偶然訪れる所から物語が展開する。一方で、夜叉ケ池の主である白雪姫とその眷属たちのやりとりも同時に進められ、人間と妖という二者の対比、境界が文雅な筆致で描かれる。
「天守物語」では、播州姫路城の天守で悠々自適に過ごす妖精夫人・富姫のもとへ、若い鷹匠の姫川図書ノ助が訪れる。序盤で描写される、富姫やその妹分の亀姫、侍女たちの人外らしく浮世離れした暮らしぶりは、読者を物語へ引き込むきっかけとしてたいへん魅力的だ。
泉鏡花作品は古文調で美しくもやや難解な表現が多く、まま敬遠されることもある。しかし本作は戯曲という形式も相まって語感の良い台詞が続くため、内容の理解という点でも、筆者特有の幽玄な作風を楽しむ点でも、鏡花作品の入門には最適だ。
本書は澁澤龍彦による解説が付されているのだが、これもまた泉鏡花の文学性を知る指南書として不足ない。人間間の対比、すなわち世俗的な人間と選ばれた人間の対立と同時に、人間と妖怪というより大きな対比が描かれるというのが鏡花作品に通底する構造だという(参考p.134)。俗世間から弾き出される「選ばれた人間」は、まさに妖怪によって選ばれ、人間と妖怪の境界を超越する存在となる。そうした構造を、情愛や悲恋といったロマン派のモチーフが彩ることで、鏡花作品に特有の幻想的かつ華やかな世界観が立ち現れてくる。
もちろん「夜叉ケ池」にも「天守物語」にも共通して、妖を理解しない人々と、妖が羨望する選ばれた人間が登場する。そして妖である白雪姫や富姫が人に対し羨望したり恋焦がれたりする様が、読者の視点には排他的な人々よりよほど人間らしく映るというのは、泉鏡花のアイロニカルな美の表れだろう。
物語の切なさもさることながら、こうした幻想文学らしい構成美が、本作随一の魅力だ。戯曲としての演出や構成も含めて、ぜひ泉鏡花への第一歩として本書を楽しんでいただきたい。
書き手:せを