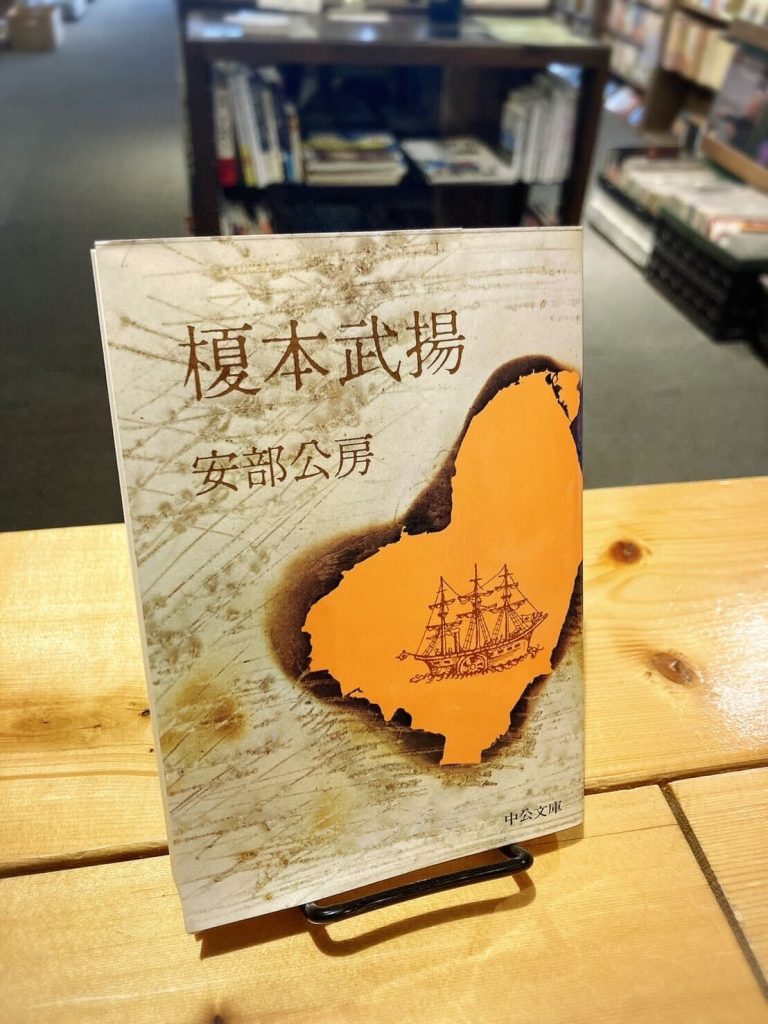著者:安部公房 出版社:中央公論新社 出版年:1990年
安部公房は不条理や鬱屈を通じて人間を描くことに卓越した作家だ。『箱男』や『砂の女』は今なお近現代の日本文学の一角を担っている。また昨年の大規模な復刊も手伝って、多くの人の手に再び安部公房の世界が広がっている。戯曲や短編などの作品を多く世に送り出した安部だが、本書『榎本武揚』は安部の作品の中でも珍しい歴史長編小説である。
函館戦争において旧幕軍を指揮した榎本武揚の行動やその真意をめぐって主人公が書籍と長い手紙を読み解いていく―という筋になっているが、一見するとその構造はやや難解なものに感じられるかもしれない。まず、1章では、厚岸の旅館に滞在した「私」が主人・福地伸六氏から榎本武揚に関する奇妙な伝説とそれに関する福地氏の胸の内を聞かされる。いわゆる一般的な小説のスタイルが取られている。一転、2章では、福地氏が後日「私」に送付した《五人組顛末記》と呼ばれる回想録と福地氏の注釈や添付された新聞記事を「私」が抜粋と補足を行なって紹介する形式が取られる。文中文である《五人組顛末記》は箱館戦争に従軍した新撰組末期の隊士・浅井十三郎の視点で語られるものであり、この隊士は函館戦争に参加した土方歳三を神格視する一方、榎本一派を目の敵にしている。3章でも続いて《五人組顛末記》の紹介、そして前章と同様に福地氏の解釈や「私」の注釈が挟まれる。2章から3章にかけての構造は語りが入れ子構造であり、かつ現在の時間軸や回想、文中文、そして回想録の資料補足といったテクストが文中には繰り返し挿入され、やや複雑な構成となっている。こうした語り手の変化や注釈が本文に挟まっているような構造は展開の掴みづらさがある。また、2章に顕著な浅井のやや穿った榎本観や疑念の強さは、さらに物事を把握するための視界を狭窄させ、事態の飲み込みをさらに複雑なものにしている。そもそもこの文中文は散逸が激しいという設定があり、時系列の激しい飛躍もあるという代物なのである。
ここまで複雑な構成を取ることにはどのような意味があるのだろか。函館戦争において、榎本武揚は劣勢に立たされ、最後は新政府軍に降伏してしまう。しかしながらその能力の高さから新政府の官僚に加わり、爵位を授かるに至っている。旧幕府側からしてみれば敵側に降伏し良い地位に召し上げられているのだから腹に据えかねる話かもしれない。榎本の行動の真意とはなんだったのか、という問いを通して描かれるのは忠誠や信念というものが呪いのように人の生き様を縛る様子であり、本書の構成の複雑さはそれを解体することの困難さを表しているかのようだ。本書では結局榎本自身の心情を描いている箇所はなく、それゆえに彼の真意は第三者の視点からしか推察ができない。それを逆手にとって、一人の像や真意を掴むことの困難さが表される。加えて、対立する信念同士の戦いに抗い、第三の道を模索することの風当たりの強さや信念というものに縛られる業を感じずにはいられない。
当たり前に抱えてきた、あるいは教唆されてきた正義や信念とは貫くに値するのか。いずれの立場こそが正義に値するのか(何故二項対立的な立場でなくてはならないのか?)。大きな枠で切り取ってしまい恐縮だが、「日本人」は全てを白か黒で割り切るきらいがあるように思えてならない時がある。問われている二つの事象の是非を問うことだけが問題解決なのではないと、安部の文学はいかなる形を取っても今の世を切り拓く重要なヒントを示している。文中で難解な構成と散々述べてしまったが、文庫版収録のドナルド・キーンの解説文、そして安部自身が64年に東京新聞夕刊に掲載したエッセイ「幕末・維新の人々」は本書を読み進めるにあたって頼もしい指針となるだろう。安部公房の名作は多い。本書も骨太ながら重要な1点として読み継がれて欲しいものである。
参照:「幕末・維新の人々」, 初出:1964年6月6日『東京新聞』夕刊, 『安部公房全集18』, 1999年, 講談社, pp.316-317
書き手:上村麻里恵