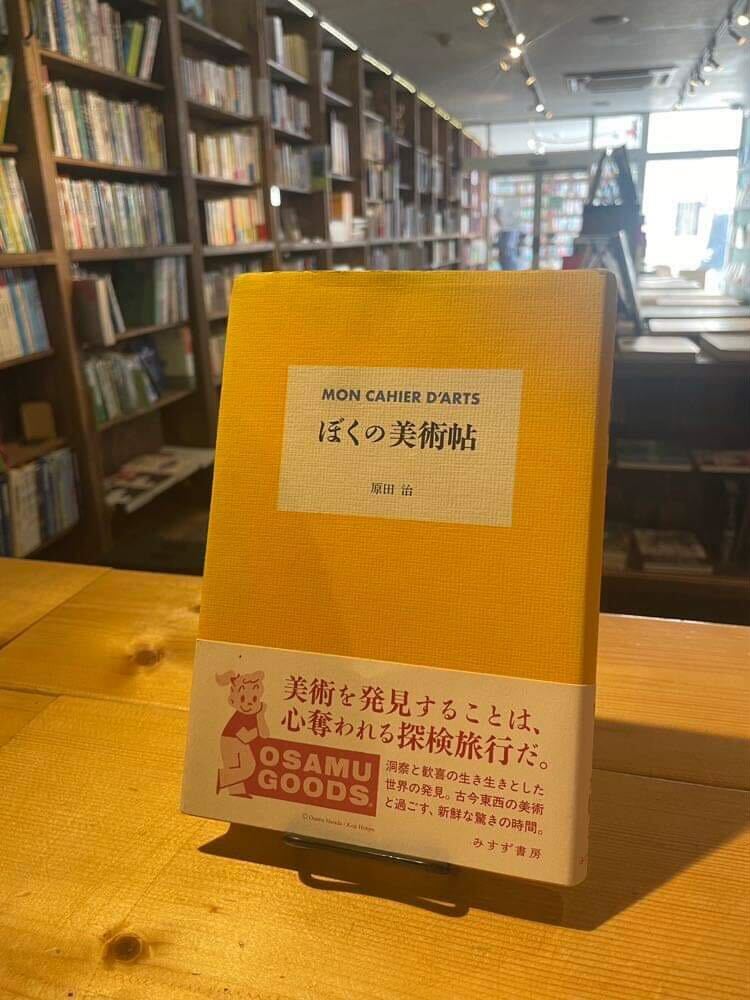著者:原田治 出版社:みすず書房 出版年:2006年
美術館で窮屈な思いをしたことはないだろうか。たとえば人気の画家の展覧会で、絵というより人を見に来たかのような混み具合に疲れたり、有名とされる作品を見てもいまいち良さがわからず決まりが悪い思いをしたり。芸術に癒されようと美術館に来たはずなのに、帰る頃には身も心も疲れ切っている、という状況に陥ったことのある人は少なからず存在するだろう。私は今でこそ大学で芸術学を専攻しているが、幼いころは美術館がなんだか偉そうな施設に思えて苦手だった。今改めて考えてみると、この「偉そう」という印象は、美術館がなんらかの価値を提示する施設であることに由来している。画家や作品の価値や評価を知った上で作品を見ることは、知的好奇心を満たすが、自由な見方が阻まれ窮屈に感じられる場合もある。今回紹介する原田治『ぼくの美術帖』は、そんな窮屈さを感じたことのある人にこそ手に取ってもらいたい一冊だ。
『ぼくの美術帖』は日本を代表するイラストレーターの原田治による美術エッセイ。1982年にPARCO出版から刊行され、その後一時絶版となっていたが、2006年にみすず書房が復刊させた。内容は好きなアーティストや作品について語る前半と、独自の日本美術史を語る後半に分かれている。前半で登場する芸術家たちは、ティツィアーノといった巨匠から、小村雪岱や鏑木清方のような挿絵を手掛けた画家たち、そして1950年代アメリカのカートゥーン作家などと幅広い。後半では、縄文土器を始点にして戦国時代の兜や浮世絵、俵屋宗達、岸田劉生など多様な作品に共通して流れる日本人の美意識をあぶり出そうと試みている。
原田は、幼少期から洋画家の川端実に師事し、加えて多摩芸術大学を卒業している。アカデミックな知見を身につけた人物であり、だからこそ本書の後半で独自の美術史を展開することができたのだろう。一方、本書の語り口には専門家的な押し付けがましさが一切ない。この絵はこう見るべき、こう感じるべき、と読者に指南するのではなく、あくまでタイトルの通り「ぼく」つまり原田の個人的な「美術帖」として文章が綴られているのだ。それがこの本の魅力である。
原田は本書のなかで、世間の評価に関係なく、自分が好きなものは好きと言う。反対に、尊敬する画家の作品であっても、好きになれない作品に対しては好きでないと言う。そして好きな理由、好きでない理由を気取ることなくありのままに述べる。これは意外と難しいことだ。特に、芸術のように良し悪しが専門家によって定められているものに対して、自分の感性に基づいた意見を述べることは躊躇されがちではないだろうか。それを、原田は楽しそうにやってのける。原田は本書の前書きで「趣味は美術」と述べており、実際美術を語る原田の口調は喜びに溢れている。その姿勢は、知識に縛られていなかった子供時代のように、自由に芸術を楽しむ心を我々に思い出させる。読者がこの本を通して得るものは、美術の知識というより、原田が美術を通して受け取った刺激やその刺激による喜びという「感情」なのだ。そうした感情に触れたとき、美術館は窮屈な場所ではなくなるだろう。新鮮な出会いの場に変容する。そうした美術館を、いつもと違う道を通って散歩をするかのように、身構えないながらもちょっとしたドキドキ感を持って歩くことができたら楽しいに違いない。
美術にはいろいろな楽しみ方があり、正解はない。ただ、美術を愛する人がもし愛することに少し疲れてしまうことがあれば、そのときはその人のそばに本書があって欲しいと思う。多くの人にとって恐らく美術を愛する最初のかたちだったであろう、気張らない、頑張らない、自分のための美術鑑賞。本書はそれを思い出させてくれるのだ。