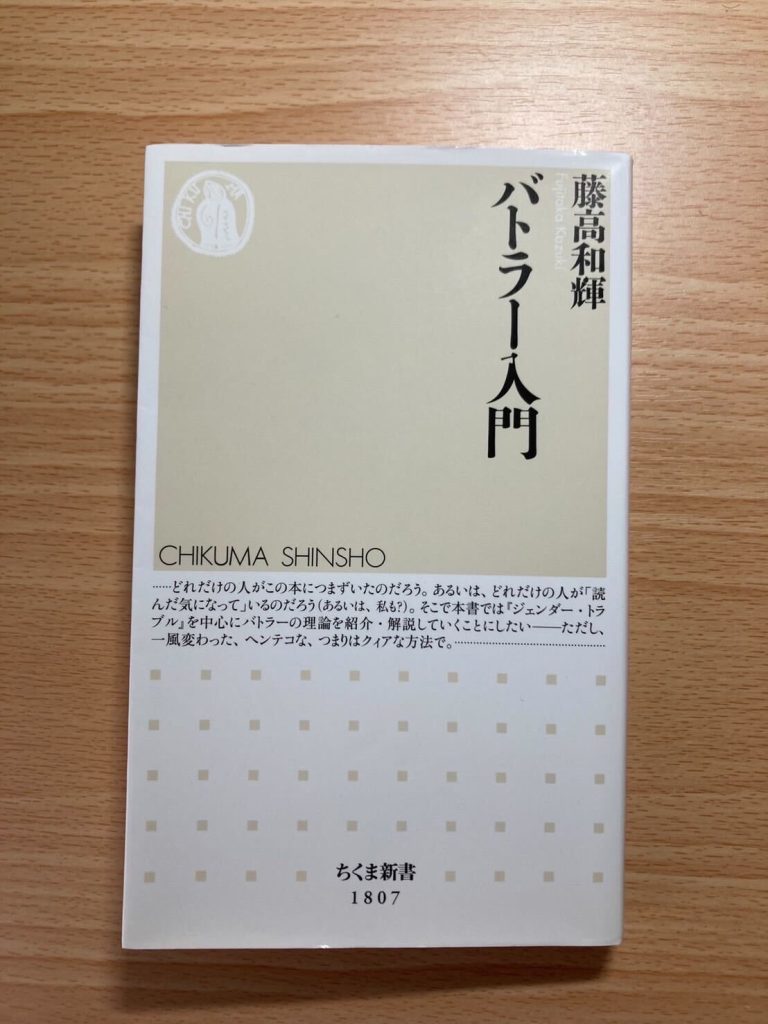著者:藤高和輝 出版社:筑摩書房 出版年:2024年
ジェンダーという言葉を聞くと、そのわからなさや多義さや曖昧さに途方に暮れ、ひょっとすると蕁麻疹が出るような気持ちになる人は割合いるのかもしれない。本書名にある「バトラー」とはアメリカの文学者ジュディス・バトラーのことであるが、もしバトラーの本を読んだことも、さらに言えばその名前を知らなくても、ジェンダーというこの「厄介で」あまりにも身近な問題に対して手を伸ばすとっかかりになるだろう。
『バトラー入門』と題されているが、議論の中心となっているのはバトラーの著した『ジェンダー・トラブル』(1990年, 邦訳新装版は2018年, 竹村和子訳, 青土社)という書籍である。『バトラー入門』の著者・藤高和輝は、バトラーの思想形成に端を発し、クィアやトランスジェンダー、ホモフォビアをテーマとした研究を行っているが、本書のことを『ジェンダー・トラブル』の「非公式ガイドブック」と称している。『ジェンダー・トラブル』はフェミニズム、レズビアニズム、クィア理論の重要な古典として挙げられるが、その内容の難解さは多くの読者の頭を捻らせてきた(私もその1人である)。藤高はバトラーの議論や思想を哲学的に解説…といった「難しいものを難しいままで」解説するスタイルはとらない。その歴史的背景やフェミニズムが辿ってきた思考の軌跡を案内する形を主として、『ジェンダー・トラブル』の重要な主張だけでなく、ジェンダーに関する固定観念を解きほぐしていく。さらに、「らしい」ジェンダーというものが持つ前提のおかしさや、この先のジェンダーが何を解体し、どのような選択肢を増やしていくのかというジェンダーで切り開くものについても論じられている。
軽快な藤高の語りは、新書らしからぬと最初は面食らうかもしれないが、議論や話の展開を抑えた非常に丁寧なガイドがなされていることがすぐにわかる。それには読み手にバトラーに対するハードルを下げるという目的もあるかもしれないが、何よりもバトラーをはじめ、フェミニズムやジェンダーの議論で奮闘してきた人々の紡ぐ言葉や主張が難解で高尚なものではなく、誰かにとって日常的で個人的なものという前提があるからだろう。だからこそ、読者もまた藤高の声を通じてバトラー、そして本書に登場する様々なフェミニズムの論客たちの声を軽快に聞き取り、リアクション―「なんで?」「どうして?」そして「そうだったんだね」「そうかもね」と言えるような―しながら読んでいける、あるいはそうすべきだと背中を押されていると捉えるべきだろう。ジェンダーは己のことでも、そして隣にいる他者のことでもある。決して専門書という限定的な領域に閉じこもるような、難解で限定的な議論になってはならないのだ。
書き手:上村麻里恵