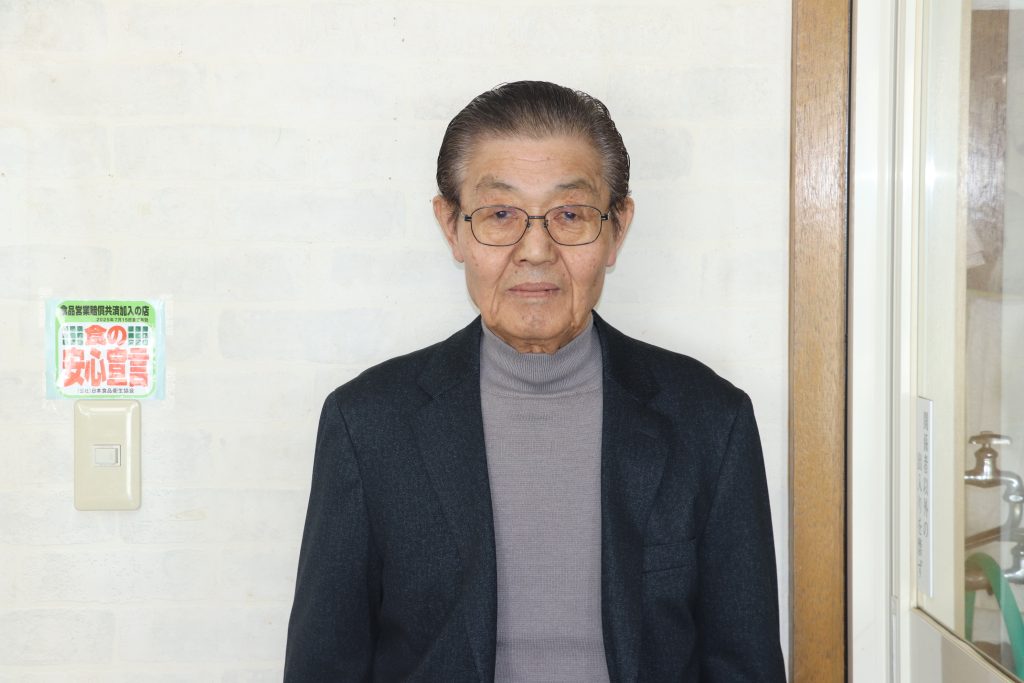下川町の公区
下川町の人口推移は表1の通りであるが、ピークは1960(昭和35)年の1万5555人(国勢調査)で、直近の2024(令和6)年9月末の2849人(住民基本台帳)と比べると80%以上の減少となっている。
下川町史によると、下川町は1959(昭和34)年に「下川町公区設置条例」を制定し、翌60(昭和35)年から「公区」を設置している。
行政事務運営の円滑化を図ることなどを目的に、行政主体で設置。広報配布、防犯街路灯の維持管理、環境美化や防犯活動、行政への要請や連絡調整などの行政事務を担っている。発足当初は29公区あったが、過疎化などの進行により、2003(平成15)年に18公区に再編・統合され現在に至っている。(公区の内訳は表2の通り)
この間、1966(昭和41)年に、各公区の連携調整・協力などを図ることを目的に、各公区長による「下川町公区長連絡協議会」が結成された。
下川町の各公区等への助成の主なものは表3の通りで、公区への交付金、公区長連絡協議会交付金、公区長委託料、公区電気料負担などとなっている。このうち、公区の電気料については、防犯街路灯の設置を各公区が要望して設置していることを鑑み、電気料については、町が3/4を負担し、残り1/4を各公区が負担している。
下川町公区長連絡協議会の会長で、錦町公区長を務める加藤幸夫さんに話を聞いた。
加藤さんは、錦町公区の福祉衛生部長、副公区長を経て、2015(平成27)年から公区長を務め、昨年4月から連絡協議会の会長を務めている。
協議会の会長を務め1年が経過した現在、「現在の役員体制になり、一定の世代交代が進んだ」と話し、「下川は条例に基づき公区を設置しているので、行政の補完的な面が強い。今まで行ってきた活動を今後も継続したい」と語る。また、「錦町は公区への加入世帯は100%で、一部の公区で未加入世帯がある」と話す。
協議会の主な事業は、戦没者追悼式の奉賛行事として剣道大会、柔道大会、芸能サークル発表会の開催、上川管内町内会自治会連絡協議会研修交流会への参加、町外視察研修など。コロナ禍で休止・縮小していた事業が、現在まで続いているものもある。
また、町の敬老会については、以前は単独又は複数の公区で実施していたが、現在は「町内の公区を二つに分けて、町と社会福祉協議会が主催してバスターミナルで実施している」と、町保健福祉課は語っている。
町内の錦町公区や一の橋公区の主な活動を紹介する。錦町公区は147世帯、15班で構成。環境美化活動、新年会、パークゴルフ大会、子ども会、交通安全防犯運動、女性部健康教室、独居高齢者等会食の集いなどの行事のほか、公区内にあるグループ「ふるさと」の運営推進会議にも公区長が出席している。
加藤さんは、「どの班長も協力的で助かっている。また、公区への未加入世帯はない」と語る。
本年度の予算規模は214万円で、このうち公区費が110万2000円、町からの交付金が14万円、防犯街路灯の電気料補助が22万1000円などとなっている。
支出面では、負担金が75万円、事業費が44万円、外灯費33万円などとなっており、負担金の中では神社運営費負担金が最も多くなっている。また、同公区は、役員報酬の中で役員の他、各班長へも班長手当を支給している。全体の予算額は200万円を超えているが、事業費の割合は低く、義務的な経費の割合が高い。
公区費については、町内の多くの公区が一律ではなく、段階制を用いている。加藤さんは「障がい者や高齢者、単身者などに配慮した相互扶助の精神から、下川では長い間、段階制で公区費を徴収している。町民も概ね理解していると思う」と語る。
錦町公区では、5段階で公区費を徴収している。標準世帯(第3区分)は月額650円で、第1・第2区分の世帯は標準より高く、第4・第5区分の世帯は低い。公区内に会社や事業所などがある場合は、特別区分として月額2000円をお願いしている。また、コロナ禍では「活動が縮小したこともあり、区費の一部を返還した時期もあった」と話す。
次に、一の橋地区では以前、子どもからお年寄りまでが集まって交流する「一の橋世代交流・福祉の集い」を1992(平成4)年から開催していた。地域住民の他、山びこ学園の利用者や職員も参加してにぎわいを見せていたが、世帯の減少、役員の担い手不足、さらには、コロナ禍などもあって、数年前から中止している。また、多くの公区や町内会が実施している環境美化活動は、クマの出没などもあり実施していない。畑直彦一の橋公区長は、「現在の主な公区活動は、年1回の総会と、神社の例大祭に合わせた親睦会が中心」と話し、クマなどの出没が多いこともあり、「住民のごみに対する意識は非常に高い」と地域の活動状況などを話してくれた。
町で公区の連絡調整や事務局を担当する町民生活課の早坂勇一課長補佐は、公区の課題や将来展望について、「人口減少や少子高齢化などにより、公区役員の担い手不足や行政事務の負担が大きくなってきている―などの課題があったことから、2021年度に『公区制度検討委員会』」を立ち上げ議論した」と話し、委員会の報告を踏まえ、「公区長委託料及び公区交付金の見直しを行った」と述べる。今後も、公区長の意見を聞きながら必要な見直しを行い「公区制度を維持したい」と語った。また、「町が主催の防災研修体験などにも、各公区長などの協力をいただいている」と話している。